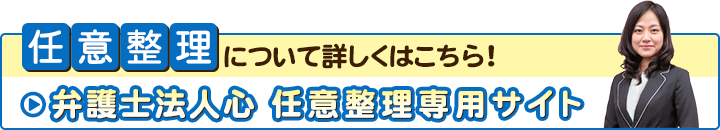個人再生ができる条件
1 個人再生とは

個人再生とは、債務返済が困難になっている方が、裁判所に債務の圧縮をしてもらい、圧縮後の残った債務を原則3年間(最長5年間)で返済していく手続きになります。
破産手続きは最終的に債務の返済義務を免れることになりますが、個人再生の場合は債務の一部は返済義務が残ることになります。
そのため破産手続きにはない、手続きを行う上での条件が課されてきます。
2 条件① 安定収入
これまでの返済額より少なくなるとはいえ、今後3~5年間の返済が続くことになります。
そのため、「再生債務者が将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が条件になります。
サラリーマンの給料が最も分かりやすい例です。
正規雇用ではなく、パートやアルバイトの方でも、職場によっては長期雇用が見込まれる場合もありますので条件を満たせる可能性があります。
老齢年金についても継続的な収入と言えますが、障害年金はケースによっては給付が止まることもあるのでケースバイケースとなります。
なお、給与所得者等再生手続きの場合は収入額の振れ幅が小さいこと(概ね20%以内)も必要となります。
小規模個人再生の場合には、再生計画を実行できるだけの安定した収入がある場合には条件を満たすことになります。
一方、給与所得者等再生手続きの場合は、手続きの名称のとおり「給与所得者」を基本的に対象としています。
そのため、自営業者の場合には条件を満たさないケースが出てきてしまいます。
どちらの手続きでも、安定した収入さえあれば良いというわけではなく、再生計画に基づく返済が可能であると裁判所が認めてくれる程度の収入額は必要になります。
3 条件② 債務額が5000万円以下
再生債権(裁判所によって圧縮の対象となる債務)の総額が、「5000万円以下」であることが必要になります。
弁護士への相談時には5000万円を超えている場合でも、消費者金融等と長期の取引があり引き直し計算をすると債務額が減少し債務総額が5000万円を下回る場合もあります。
一方、弁護士への相談時には5000万円を下回っていても、遅延損害金が発生して5000万円を上回ってしまうこともあります。
なお、再生債権には住宅資金特別条項を使う場合の住宅ローンや公租公課(税金等)は含まれません。
4 条件③ 債権者からの反対(小規模個人再生の場合)
個人再生の場合、今後、各債権者に対して圧縮後の債務をどのように返済していくかの計画を作ることになります。全ての債権者がこの作成した計画に賛成してもらう必要まではありません。
小規模個人再生の場合は、「債権者の半数以上または債権額の過半数を持つ債権者が反対した場合」には計画が通らなくなります。
一方、給与所得者等再生手続きの場合は、裁判所は債権者から意見が出れば参考にしますが、債権者の意見に拘束まではされません。
5 条件④ 過去7年以内に破産免責等を受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生手続きは、認可するかしないかについて債権者の意見に拘束されず裁判所が一刀両断に判断する手続きになります。
そのため、破産手続きにおける免責に近いものであり、裁判所の一刀両断の措置は、そう何度も認められないということもあり、給与所得者等再生手続きの場合は「過去7年以内に破産免責、個人再生のハードシップ免責、給与所得者再生の認可を受けていないこと」が条件になります。
6 手続きをお考えの方は弁護士へ
個人再生も破産手続き同様、弁護士を使わずに手続きを進めることもできます。
但し、破産手続き以上に複数の条件が求められることから、弁護士を使わずに手続きを進めることは難しいと言われています。
さらに、住宅資金特別条項を使う場合には、そのための条件も求められています。
そのため、手続きをお考えの方は専門家に相談することをお勧めします。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生をする場合の流れ
これから個人再生をしようとお考えの方の中には、どのような流れで進んでいくのか知りたいという方は多いと思います。
そこで、個人再生をする場合の基本的な流れについて説明していきます。
2 個人再生の申立てへ向けた準備

個人再生を裁判所へ申立てする場合、様々な資料、書類を提出する必要があります。
例えば、収入に関する資料として給与明細書や源泉徴収票、財産に関する資料として通帳の履歴、車検証、保険証券、退職金の額が分かる資料、毎月の収入支出の状況をまとめた家計の状況などを提出する必要があります。
弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士が受任通知を送ることで原則として債権者からの督促や借金の返済が止まりますので、その間に弁護士費用の分割払いを行ったり、これらの資料を準備したりします。
3 裁判所への申立て→補充事項への対応→開始決定
申立ての準備が整ったら、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
申立てを行うと、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任されます。
裁判所によっては、案件によって個人再生委員を選任するか否か裁判所が判断するところもありますが、東京地裁(八王子に在住の方は東京地裁立川支部です)の運用では、全件個人再生委員が選任されることになっています。
個人再生委員が選任されると、個人再生委員による収入や財産等の調査が始まり、調査の結果、個人再生の手続きを開始するのが妥当であると判断されれば、裁判所から開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定が出されると、再生計画案という、減額後の借金の返済計画案を作成し、提出する期限が定められます。
期限までに再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。
5 付議決定
個人再生のうち、「小規模個人再生」と呼ばれる手続を行う場合、債権者の多数決の手続きを経る必要があります。
裁判所に再生計画案を提出すると、裁判所から債権者の多数決に付す決定が出されます。
これを付議決定といいます。
なお、債権者の多数決において、債権者数の過半数又は債務額の半額以上の債権者の反対があると、小規模個人再生の手続きは失敗してしまいます。
他方、もう一つの給与所得者等再生という手続きでは、多数決はありません。
6 認可決定・認可決定確定
小規模個人再生の場合、債権者の多数決において反対多数にならなければ、裁判所から認可決定が出されます。
給与所得者等再生という手続きの場合、裁判所が再生計画案のチェックを行い、特に問題がなければ認可決定が出されます。
そして、認可決定から約1か月後に認可決定が確定します。
7 再生計画の履行
認可決定が確定した後、再生計画の履行、すなわち減額後の借金の支払いが始まります。
法律の規定上は、再生計画の履行が完了して初めて、減額された借金の支払い義務が免除されます。
もしも途中で返済が滞った場合、借金が復活してしまうおそれもありますので、最後まで返済を続けることが大切です。